
人と技術の新しい繋がりを目指して。
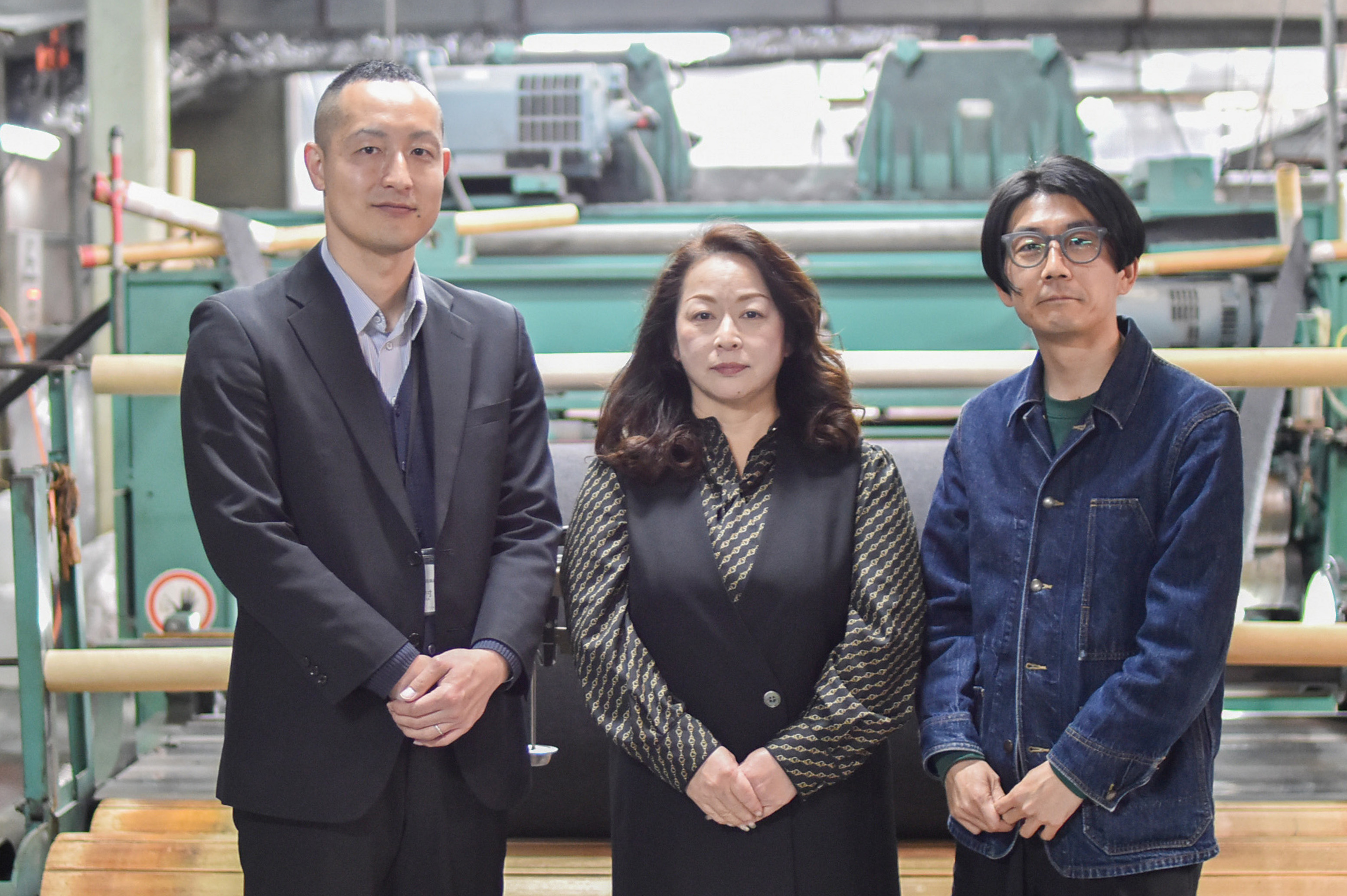
左から、野村さん、林さん、青木さん。
ーでは初めに、皆さんの自己紹介をお願いします
野村 :市産業政策課の野村です。専門家ではないので、いろんな人を繋げることが私の仕事だと考えています。今後も事業を通じて、企業の皆さん同士の連携や、企業と市民の方々との繋がりを大切にしていきたいと考えています。
林:岐阜化繊工業会社の林です。弊社は市内でニードルパンチ不織布を製造している会社です。空気清浄機やエアコンのフィルター、男性用スーツの芯地、肩パット、また手芸用のキルト綿、他にも車両や屋上庭園などに使用されている素材を作っています。「I LOVE 不織布」です。
青木: TENTというデザイン会社をやっています。受託ではなくて、「一緒に何を作るか考えて」というお仕事が多く、「こういうのやりたいんです」っていうのがあってからやる、というスタイルです。「デザイン」というには珍しく、ゼロから作って、作ったものをどうやって伝えて売っていくかまで全部行っています。
ー現在、各務原市が取り組んでいる「企業変革促進プロジェクト」とは何でしょうか
野村 :「企業変革プロジェクト」と「オープンファクトリー」という2つの事業で構成されています。中小企業が時代の流れに対応するために、新しいことにチャレンジすることを応援するような事業です。オープンファクトリーについては、各務原市は県下トップのものづくりのまちと言われていますので、ものづくり企業が工場を開放し、来場者にその技術や魅力を知ってもらうプロジェクトです。プロジェクトを通して、最終的には選ばれるまち、持続可能なまちにしていきたいと考えています。
各務原は、有効求人倍率が全国や岐阜県の数値よりも高めで、企業が人材確保に困っているという現状です。良い企業があるのに皆さんが知らないというのが各務原市の課題の一つになっています。ぜひ皆さんに企業を知ってもらい、選んでもらえる、そんなまちにしていきたいと思っています。

ー「企業変革プロジェクト」では青木さんを講師にお招きして、セミナーやワークショップを行ったそうですが、具体的にどのようなことを行なったのでしょうか?
野村 :今年度のセミナーとワークショップで、セミナーが4回、ワークショップは同じ企業に連続3回参加する方式で実施しました。主にTENTさんの得意分野である「新商品開発」をテーマに、ゲストを迎えたクロストークや、新商品開発の手法を学ぶワークショップを行いました。
ーセミナーでは実際どのようなことを話されるんですか?
青木 :ワークショップでは、「新商品開発」とはメタファー(例え)だと伝えました。実際やることは、ゼロから何かを考えて思いつき、それを実行して世に伝えていくという、ゼロから最後までの工程のことを言っていて、それをどう回すかということです。そういう意味では絶対知っておくと武器になると思っています。できるだけ抽象化して、教育事業などいろんな分野の人でも応用が利くような形でやろうとしているというのが実際のところです。
セミナーは商品開発で呼ばれましたが、私たちTENTの特徴は、「作る」だけでなく「伝える」もやっていることです。一般的にはそれを分離している方が結構多くて。求人=広報頑張らなきゃとか。そうではなくて、作っている工程そのものが広報ですし、作ることも伝えることも全部繋がっていて、その全体の視点を持とうという話を、セミナーでもワークショップでもずっと話しています。

ー 青木さんは過去にも様々な企業と商品開発をされていますが、今回のようなプロジェクトが企業側に与える変化というのは、どのようなものになると感じられていますか?
青木:変化が起きて売上というのは後からついてくるとして、人の繋がりのようなものが増えます。繋がる人数が増えるというか。それと同時に、仕事っぽかったものが、遊びっぽくなるというか。語弊があるんですけど、結局人って人と人の繋がりでやるのが結構好きなんだなというのが多分根っこにあると思うんです。「これは仕事だから」と言って日々事務的に処理するものがあった状態から、人と人がコミュニケーションを取って何か喜んでもらえたとか、そういうことの数がすごく増えていく印象を受けます。こういうことが各務原でもできるといいですねという、頑張るぞという感じです。
ー岐阜化繊工業さんは自社のオープンファクトリーにも力を入れてらっしゃると伺いました
林:まず、皆さんにここに岐阜化繊工業があることを知っていただく、名前を知っていただく。そして何をやっているかも知っていただくという思いで、オープンファクトリーを行いました。今回のオープンファクトリーでは、「いつも前を通っていて何をやっているかわからないけど、こういうことをやっていたんだね」というご近所の方も多かったです。工場の向かいの方も飛び込みでいらっしゃいました。
以前までは企業秘密などの理由で工場にも入れなくて、市にも「そんな写真はちょっと…」という対応をしていました。とはいえ、製品名などが入っているような写真は困りますが、基本的にはオープンにしたって何ら問題はないという考えです。気軽に来て見てもらえることを一番大切にしています。それが「安心安全」というか「変なことはやっていませんよ」というメッセージになります。そういう意味では、オープンファクトリーはすごく良かったなと思います。

ー以前からオープンな社風でしたか?
林:以前はとても閉鎖的でしたが、私が変えてきました(笑)。
青木 :私も以前、子どもを連れてオープンファクトリーに行ったことがあるんです。子どもって、反応がすごくわかりやすいじゃないですか。会社の説明をされても全然聞いていなくて、「早く帰りたい!」って言うんですよ。でも、その場にいる人が「ここをこうやって工夫したんですよ」と、ちょっと自慢するように“個人”が見えてくると、途端に興味を示してテンションが上がるんです。
会社の人って、どうしても会社の説明や「業務」の話をしたがるんですけど、見に来ている人は“人”を見たくて来ている。そのギャップがすごく大きいなと感じました。「いやいや、僕じゃなくて会社が……」って皆さんおっしゃるんですけど、「いやいや、自分の話をすればいいのに」と思うことがよくあります。
林:企業側としては、やっぱり個人よりも会社として伝えたいというのはありますね。
青木 :その気持ちはすごくわかります。でも、「I LOVE 不織布!」というテンションで語るのか、単なる業務として話すのかで、同じ言葉でも聞こえ方がまったく変わると思うんです。

オープンファクトリーの様子
ー岐阜化繊工業では「息する植木鉢」などの商品開発なども積極的に挑戦されていますね
林:商工会議所さんから、ブランディングセミナーをやるから今ある商品のブラッシュアップをしようとお声がけいただいて。既存商品を見ていただいたところ、「これじゃ全然ダメ。次までに何か持ってこい」と言われて。(笑)改めてうちの強みってなんだろうと、社内で話して、屋上庭園を作ってるから植木鉢が良いんじゃないかという話が出たので持って行きました。
最初は土を入れる想定でしたが、不織布自体に根を張るから、土を使わずに不織布の端材を培地にして、そこに直接植える仕組みにしました。陶器の植木鉢、プラスチックの植木鉢、不織布の植木鉢で比較実験もして、ジャガイモを育てて収穫もできました。
ー商品開発に対するモチベーションの高さを感じます
林:コロナ禍の頃に比べると今はすごく忙しいですが、新商品開発は仕事というよりも「本当に自分のやっていくべきこと」としてやっている感じです。必ず頭のどこかで新商品のアイデアは常に考えています。今まで、自分の所の不織布を出すために商品開発をしようと、まずはそれを考えていました。けど、異業種の方と手を組んで、不織布と何かを組み合わせた商品開発をしていくのが一番いいと思うようになりました。逆にそういうことをしなくなってしまうと終わっちゃうかなみたいな。他の人の手を借りるってことは大事だなと感じながら今やっています。
もちろん根幹となる製造業っていうのが一番大事なことで、でも枝は常に伸ばしていって、どこでそれが太くなっていくのかわからない。でもそれを何とか太くしていきたいなと思ってやっています。
青木 :多分、「新しいことをしなきゃ」と思っても、実際には行動に移さない人の方が多いと思うんです。でも、実際にやっている人は「新しいことをやらないと終わる」と思っているんですよね。だから、どちらかというと「チャレンジ」というより、「保険」として新しいことをしているという考え方が近くて、根本的なスタンスがまったく違うんだなと感じました。それから、会社をオープンにすることをチャレンジだと捉えている人が多いですよね。でも、普通の人間って「知らない=嫌い」なんです。知られていないことはマイナス(=みんなに嫌われている)だと考えた方がよくて、知ってもらえて初めてゼロになるというか。実際は、「知られていないこと」は、みんなが思っている以上にリスキーなことだと思います。
林:あとは、本当に楽しいかどうか。仕事の一部としてやってしまうと「やらなきゃいけないこと」になってしまうけれども、そうじゃなくて面白いな、楽しいなっていうのが一番だと思います。
青木 :川の水に子どもが石を並べると流れが変わるように、新しいことをすると世界の流れも変わると思うんです。「変えられるんだ」という感覚って楽しいなと思っていて。例えば、自分の家庭や工場の一部分を少し変えるだけで、明日が変わる。その手触り感というか、「世界を改変する権利が自分にもある」という実感が、楽しさにつながるのかなと。大げさに言うと、そういうことなのかなと思います。うちではくじ引きの例え方をよくしています。ヒットするかしないかはくじなんだからいっぱい引かないとわかんないし、しかもくじがお得なことに、消費期限のないくじなんです。
引いて置いておくと5年後に爆発的に売れたりとかするので、とりあえず引いておけば良いじゃんと思います。
林:とりあえず世に出していこうという感じですよね。世に出さないと誰にもわかってもらえないので。あとはどう世に出すかですね。
青木 :売れなくて失敗することを恐れる方多いんですけど、売れなくて有名にならなくて失敗すると、誰にも知られないので。ヒットしない限りはバレないので大丈夫です。(笑)

岐阜化繊工業が開発した「息する植木鉢」
ー青木さんは、今回のプロジェクトで今後このまちにはどのような面白い動きが起こると思いますか?
青木 :すごく冷酷なことを言うと、地域のすべての人が同じテンションに向かうのは無理だと僕は思っています。
ただ、昔は今いる地域しかなかったので、たとえ地域に面白い人がいても、同調圧力などでやりづらかったと思うんです。でも今は、地域の中の面白い人が、全国や世界の面白い人と気軽に連絡を取れるようになりました。そうやって垣根を超えてネットワークがつながることで、お互いに励まし合いながら「やるぞ!」という発火点が生まれ、次第に地域にも広がっていく——そんなイメージです。
だから、「この地域を変える」というよりは、そうしたつながりを生み出す手伝いができればいいなと思っています。まずはピンポイントでの取り組みになるとは思いますが、外とつながることで一気に燃料が投下される。その結果、「この地域では理解されない」「この会社では分かってもらえない」と感じていた人が、別の誰かとつながることで突破口を見つけられる。そういう流れが生まれることを実感しているので、まずはそこからだと思っています。
ー今後挑戦したいことや、思い描いている未来はありますか?
林:今やっていることはこれからも続けていこうと考えています。その中で、誰と一緒にできるか、誰と組めるか、どこと協力していくかが重要になってくると思います。やはり自社だけでは限界があるので、他のものと組み合わせて、新しい何かを作っていくことは絶対に必要だと感じています。それが何なのかはまだ分かりませんが、まずは自社の不織布をしっかりと世に出すこと。そのうえで、不織布を使ったものづくりに加えて、プラスαで一緒にできること、協力できる企業や素材、アイデアを常に探し続けていきたいと思っています。
野村 :市としては、オープンファクトリーも企業の皆さんから「やりたい」という声が上がって始まったプロジェクトですし、その他にも企業の皆さんの要望からスタートしたプロジェクトが進んでいます。今後も、企業の「やりたい」という声に応え、しっかり応援できるような体制で進めていければと思っています。
撮影協力:岐阜化繊工業株式会社
取材日:2025年2月
※出演者の所属・役職は取材時のもの
小澤 ことはozaco design
2019年に家族で各務原市へ移住してきました。普段はフリーランスとして、デザインを中心にライティングなどのお仕事もさせていただいています。お仕事を通して暮らしているまちに何か還元できて、結果的に周りの大好きな人たちの幸せにつながる。そんな働き方がしていければ、とても幸せです。